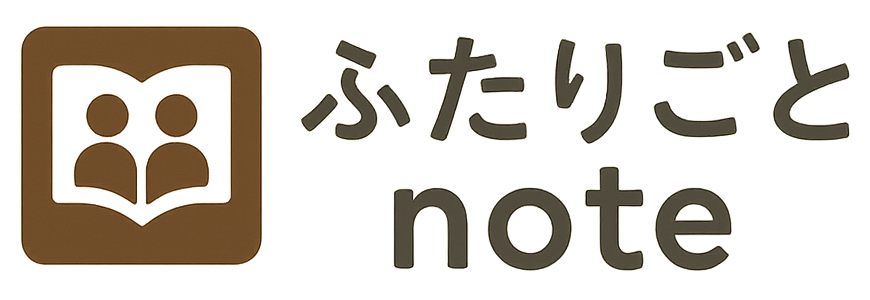OCRって難しい技術?名刺トラブルから学んだ文字認識の進化
DXの裏側にあるOCRの限界と工夫を、身近な体験からわかりやすく解説します。

名刺を写真で取り込んでデジタル化する際に、OCR(文字認識)を使ってみたところ、メールアドレスの小文字が大文字に読み取られてしまい、送信したメールがバウンスしてしまったことがありました。
「OCRってまだまだ精度が不安定なんだな」と思う一方で、ふと「そういえば昔からOCRは難しい技術だと言われてきたよな」とも感じました。
そこで今回は、実体験をきっかけに 「OCRはなぜ難しいのか」「どう進化してきたのか」 を調べてみました。
OCRとは?
OCR(Optical Character Recognition)は、画像の中の文字をコンピュータに認識させる技術です。
身近な例では、
- 名刺の自動データ化
- 請求書から金額や会社名を抽出
- 書籍や雑誌をスキャンして検索可能に
など、あらゆる場面で使われています。
OCRが間違える理由
私のように「メールアドレスが誤って認識される」ケースには、次のような要因があります。
- 文字の形が似ている:l(小文字エル)と I(大文字アイ)、0 と O など。
- 特殊文字列に弱い:自然文に最適化されているOCRは、メールアドレスやURLなどの記号混じり文字列は苦手。
- 補正処理の不足:OCR後に「小文字化」や「形式チェック」をしないと、誤りがそのまま残ってしまう。
👉 つまり、精度の問題だけでなく、後処理の設計不足も大きな原因です。
OCRは日本語だから難しいの?
よく「日本語OCRは難しい」と言われます。これは一部正解で、一部誤解です。
- 世界共通の難しさ
低解像度・影・複雑なレイアウトは、どの言語でも誤認識の原因。 - 日本語特有の難しさ
漢字の種類が多い/ひらがな・カタカナ・英数字が混ざる/縦書き・横書き両対応。 - アルファベット言語の難しさ
英語でも rn と m、I と l の誤認識はよく起きる。
👉 結論:OCRが難しいのは全言語共通。ただし日本語は特に難易度が高い。
OCRの進化の歴史
調べてみると、OCRは70年以上の歴史を持つ技術でした。
- 1950年代:銀行小切手や郵便番号の読み取りで実用化。専用フォント(OCR-Aなど)登場。
- 1980〜90年代:PC用OCRソフトが普及。日本語OCRも商用化。
- 2000年代:スキャナ+OCRでPDFを検索可能に。
- 2010年代:GoogleのTesseractなど、機械学習ベースのOCRが登場。
- 現在:ディープラーニングで手書き文字や多言語対応が進み、「文字を読む」から「意味を理解してデータ化」する時代へ。
どう付き合えばいいのか?
OCRを使う上で大切なのは、「完全自動化」に期待しすぎないこと。
- 自動補正を入れる:メールアドレスは必ず小文字化+形式チェック。
- 人力を最小限に残す:重要なデータだけ目視確認。
- サービス選びを工夫:Sansanのように人力補正を組み込んだサービスを使うのも手。
👉 DXの本質は「人力ゼロ」ではなく、人力を最小限にして効率化する仕組みをつくること。
まとめ
- OCRは便利だが誤認識は避けられない。
- 日本語は特に難しいが、英語でも誤認識はある。
- 進化の歴史を知ると、今の限界と可能性が見えてくる。
- 大切なのは「OCR後の処理」と「人力をどこで挟むか」の設計。
名刺OCRでのちょっとした失敗が、OCRという技術の奥深さやDXのリアルを学ぶきっかけになりました。

なつ
好奇心多め。スタートアップで働くマーケター。旅行LOVE!