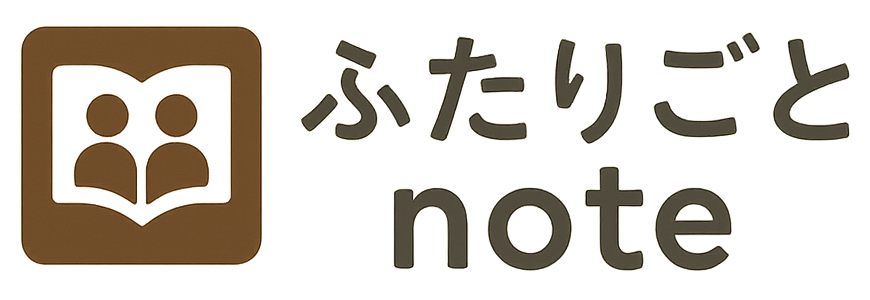工場のあとに、まちはどうなる?──これからの『産業』を考える
日産追浜工場閉鎖のニュースをきっかけに、製造業が担ってきた役割を振り返りながら、観光・IT・食・ベッドタウンの文脈を整理し、これからの「まちの産業」とは何かを考えました。

はじめに:ニュースをきっかけに
日産の追浜工場閉鎖のニュースを見ました。
工場は単なる生産拠点ではなく、雇用を生み、住宅を支え、学校や商店を成り立たせ、インフラを整える存在でもありました。
その工場が閉じられるとき、「町はどう変わっていくのだろうか?」という疑問が自然と浮かびました。
今回の記事は、その問いを入口に、いくつかの方向から調べ、考えてみた記録です。
結論を断言するものではなく、「今後どうしていくべきだろうか」という検討の途中経過として書き残しておきます。
製造業が担ってきた役割
かつての製造業は、まちづくりに直結していました。
- 工場が立地する → 雇用が生まれる
- 雇用がある → 人口が定着し、住宅・学校・商店が生まれる
- 人が集まる → インフラ投資が正当化される
この流れが非常に明快だったため、住民や行政にとっても「この町の未来像」がわかりやすかったのだと思います。
しかし今は、グローバル化や自動化で「雇用を大量に吸収する」力が弱まりました。
結果として、地域の骨格を支える役割を製造業に期待するのは難しくなっていると感じます。
代替としての観光・ITの可能性と限界
よく「観光」や「IT」が製造業の代替として語られます。
ただ調べていく中で、いくつかの難しさが見えてきました。
- 観光
観光は外からお金を呼び込むことができますが、資源や立地に強く依存します。すべての地域が観光に向いているわけではなく、安定性にも課題があります。 - IT
ITは高付加価値を生む産業ですが、雇用規模が大きくなく、地域に物理的な基盤を残しにくい。リモート中心だと「人は住んでいても経済が落ちない」状態にもなりかねません。
つまりどちらも重要ではあるものの、単独で「まちの産業の柱」としては弱いように感じました。
食・一次産業の持つ可能性
そこで改めて考え直したのが「食」です。
観光を成立させるのにも食は不可欠であり、一次産業(農業・漁業・畜産)が支えています。
一次産業は土地と強く結びついているため、地域性や教育的価値を伴いやすい。
加えて、デジタル技術と組み合わせることで販路拡大(ECやサブスクなど)にもつながります。
もちろん規模は製造業に及ばないかもしれませんが、持続性と地域性の面では、今後のまちを支える基盤になりうると感じました。
ベッドタウンという中間領域
さらに、自分が暮らすような「都市近郊のベッドタウン」にも目を向けてみました。
田園都市線沿線はその典型例ですが、ここでは固有名詞ではなく「ベッドタウン」という地域類型として捉えます。
ベッドタウンは、
- 子育て世代が相対的に多い
- 生活利便性は高い
- しかし観光資源や大きな産業は乏しい
という特徴を持っています。
つまり、人口はあるのに「産業の柱」が見えにくいのです。
では、ベッドタウン型の地域は何を拠り所にしていけばいいのか。ここが今後の大きな検討課題だと思います。
現代のビジョンがわかりにくい理由
工場の時代は「この企業が来れば安泰」という一本のストーリーがありました。
一方、今の観光・IT・一次産業・教育などを組み合わせたビジョンは、どうしても抽象度が高く、成果も時間をかけないと見えてきません。
つまり、現代は「一本化された分かりやすい未来像」を描きにくい社会になっているのだと思います。
この“見えにくさ”そのものが、合意形成や行動のハードルになっています。
教育と「学びの場」の再設計
そこで最後に教育の視点に戻ります。
こうした価値観の変化を社会に根づかせるには、学校教育だけでなく、地域全体での学びの場づくりが必要だと思いました。
- 子どもが商店街で小さな出店をする
- 親子で農業や漁業に関わる体験をする
- 図書館やカフェで地域の課題について語り合う
こうした「生活と学びがつながる場」が、地域に根づいていくこと。
それが、わかりにくくても持続する未来を形づくる一歩になるのではないかと感じました。
まとめとこれからの検討
今回、追浜の工場閉鎖というニュースをきっかけに、
- 製造業がまちの骨格を支えてきた歴史
- 観光やITの可能性と限界
- 食や一次産業の地力
- ベッドタウンという中間的な地域の難しさ
- 教育や学びの場の重要性
を整理してきました。
最終的に残った問いはシンプルです。
これから私たちは、どんな要素を組み合わせて「まちの産業」と呼べるものを育てていけばいいのだろうか?
その答えはひとつではなく、地域ごとに違うと思います。
ただ、見えにくさや複雑さを避けずに受け止めること。そこから始めるのが大事なのではないかと感じました。
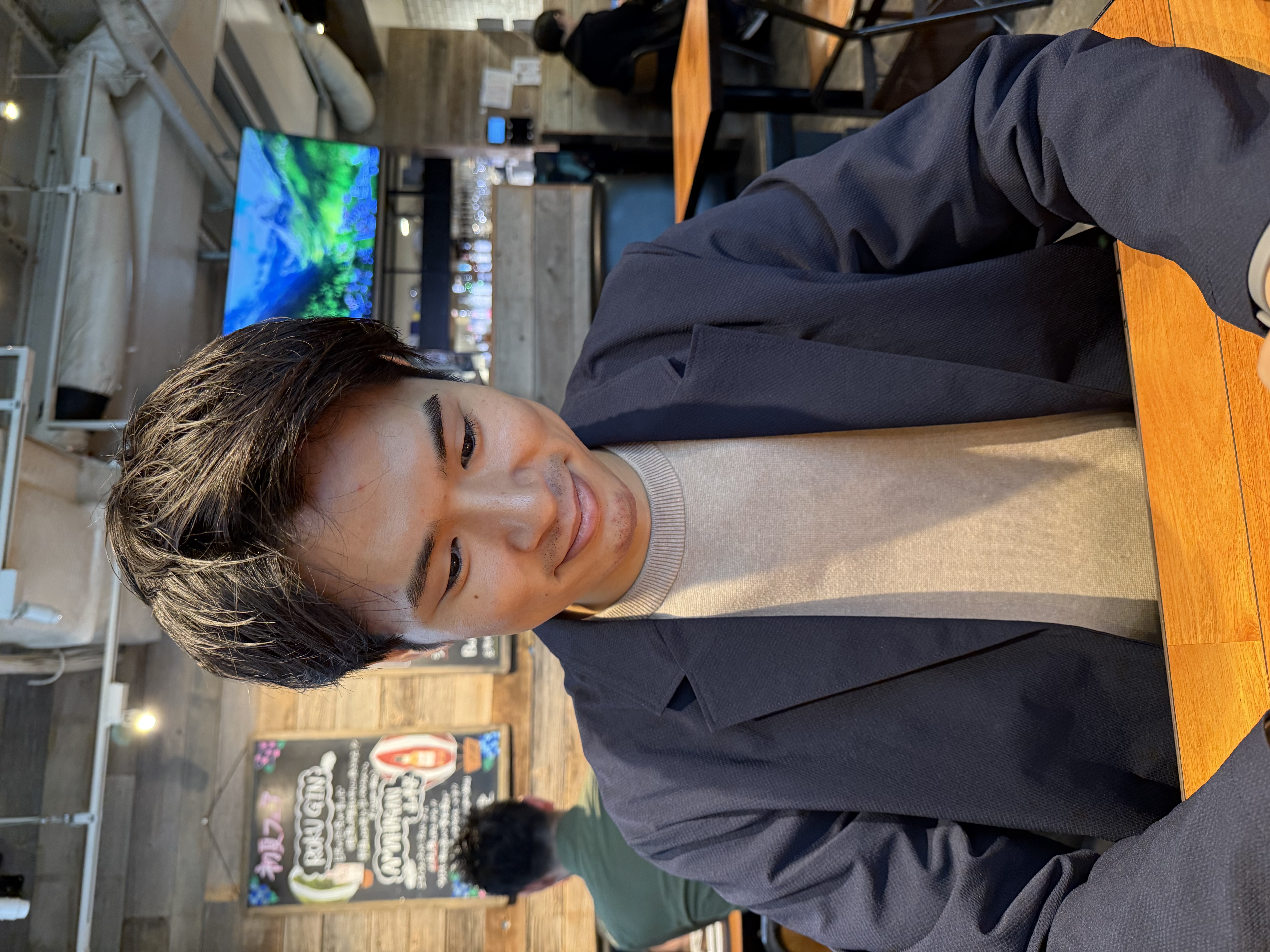
りょう
いろいろなことを考えるエンジニア