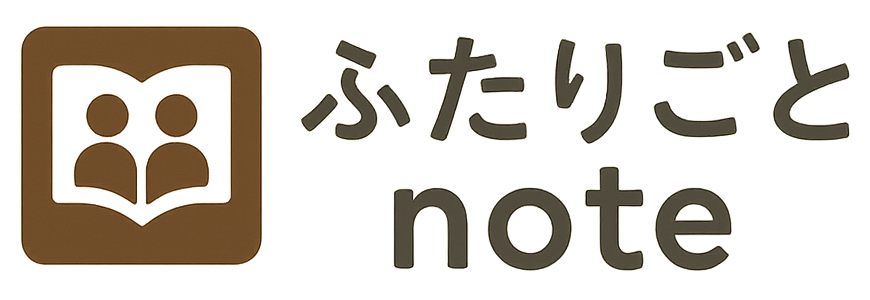台湾旅行で気づいた「なぜ?」が止まらない:街・鉄道・ビルから読み解く社会のロジック
台湾旅行中にふと感じた「ベランダの植物が多い」「ビルが茶色くて古びている」「空港線がクネクネしている」──そんな素朴な疑問から始まり、日本との違いを次々と掘り下げてみました。 交通・都市開発・公共空間・文化意識の違いが、ここまで街並みに現れるのか?台湾という街の“ロジック”を読み解く思考の旅。

はじめに
旅行中にふと感じた「小さな違和感」から、思わぬ発見が連続することってありませんか?
今回訪れた台湾では、まさにそれが連続でした。
街を歩きながら、「なんでベランダにあんなに植物が?」「この建物、やたら茶色くて古いけどなぜ?」「この空港線、なんでこんなにクネクネしてるの?」と、“旅の景色”が次々と“社会の謎”に変わっていく感覚。
本記事では、そんな台湾の街並みや交通、建築、都市開発の「なぜ?」を、日本と比較しながら徹底的に深掘りしていきます。
🏙 ベランダに生い茂る植物たち:暮らしと自然の距離感
台湾のマンションでは、ベランダに大量の鉢植えや木が並んでいる風景が当たり前。
これは気候的な要因(亜熱帯〜熱帯で植物が育ちやすい)だけでなく、都市生活の中に自然を取り込む文化的志向や、風水・健康意識とも関係しています。
また、バルコニー空間が建築構造上大きく確保されていることも要因。見た目以上に生活に根ざした選択なのです。
🧱 1階が歩道になる「騎樓(チーロウ)」構造とは?
台湾の都市部では、2階以上が張り出し、1階が屋根付きの歩道になっている建物をよく見かけます。これは**「騎樓」**という台湾独自の建築文化。
雨よけ・日よけ機能を持ちながら、1階を商店、2階以上を住居とする商住混在の都市設計で、東南アジアの華人社会に共通する構造でもあります。
これにより、人々は雨の多い台湾でも快適に歩けるという、実用性に裏打ちされた伝統が続いているのです。
🚌 バスが道路の真ん中? 公共交通の設計思想が違う
台北では、バス専用レーンが道路の中央に設けられ、中央分離帯にバス停が設置されている構造が見られます。
これはバスの定時運行を確保する都市設計の工夫であり、路上駐車の影響を避けつつ大量輸送を支える戦略的な配置です。
可変式の専用レーン運用など、日本ではあまり見かけない先進的な取り組みもあります。
⛩ なぜ地下街が発達していないのか?
雨や日差しを避ける工夫として地下街が発達しそうな台湾ですが、実際には地下街は限定的です。
その背景には、
- 高温多湿で地下が不快になりやすい
- 地盤・地下水位・洪水リスクが高い
- 騎樓など地上空間で事足りる といった合理的な都市設計上の選択があります。
🏪 セブンとファミマばかり。ローソンがいない理由
台湾のコンビニは**セブン-イレブン(統一)とファミリーマート(全家)**の2強体制。
ローソンは台湾に未進出で、参入余地もほとんどありません。
その理由は、台湾ではすでに2強が
- 地元財閥と連携しきっている
- 市場が飽和している
- 独自商品や生活インフラ機能まで浸透している
といった点で、後発が割り込む余地が極めて少ない市場だからです。
🌏 台湾の「親日感情」の深層
台湾では多くの人が日本に対して親しみを抱いていますが、それは表面的な印象ではなく、歴史と実利、共感の積み重ねに基づいています。
- 日本統治時代のインフラ整備への評価
- 戦後の国民党政権との相対比較
- 災害時の相互支援(例:東日本大震災)
- 日本文化(アニメ・旅行)への憧れと馴染み
このような複合的な要因が、「親日」という単語の奥に広がっています。
🎮 ゲーセンの多さとクレーンゲームブーム
台湾の街中には、小さなクレーンゲーム専門店が至る所にあります。
これは「夾娃娃機熱(ぬいぐるみ機ブーム)」と呼ばれる社会現象であり、
- 設置規制の緩さ
- 投資・副業目的での店舗運営
- SNS映えやコレクター心理 がブームを後押ししています。
🏗 鉄道整備と都市開発が見事に連動
特に桃園空港MRTでは、新駅周辺にタワーマンションが林立するような再開発が進行中。
これは
- 空港アクセス鉄道という公共投資
- 土地の確保しやすい郊外
- MRT駅近という価値のブランド化 がうまく重なり、「交通×都市開発の好循環」を生み出しています。
🚧 一方の日本はなぜ失敗しがちなのか?
近年の日本では、
- 地権者調整の難しさ
- 鉄道とまちづくりの縦割り
- 駅だけ作ってまちが育たない構図 が多く見られ、台湾のように「駅ができて街も育つ」構図は少数派。
成功例としては 武蔵小杉、豊洲、柏の葉 などがありましたが、スピード感と制度設計で台湾に及ばない面も多くあります。
🚫 MRTで飲食禁止? 徹底された清潔主義
台湾の地下鉄では飲食が法律で禁止されており、違反すれば罰金です。
- 高温多湿で衛生リスクが高い
- 一律禁止の方がトラブルが少ない
- 市民意識としてルールが徹底している
という背景があり、最初から「静かで清潔な空間」をデザインしたことが奏功しています。
🌿 空港線から見える「ジャングルみたいな森」
桃園MRTの車窓から見える森が日本とまったく違うのは、以下のような理由によります:
- 亜熱帯気候で植物が密に繁茂
- 常緑広葉樹+シダ・ツル・竹が混在
- 野生に近い「人の手が入っていない」密林状態
まるで東南アジアのジャングルを見ているかのような生命力に満ちた風景が、日本との違いを強く印象づけます。
✍️ まとめ:台湾という「都市観察の宝庫」
台湾旅行は、単なる観光地巡りではなく、「都市設計」「インフラ」「社会文化」を観察することで、知的に楽しめる旅になります。
同じアジアでありながら、日本とはまったく違うルール、設計思想、歴史背景があり、それが街の「見た目」に現れているのです。
📌 おまけ:この記事を読んでから台湾に行くと…
- 騎樓の下で「これは文化なんだな」と思える
- 駅前のタワマンが“戦略的配置”だとわかる
- MRTに乗るときに飲み物をしまいたくなる
- 森を見るだけで気候帯を想像できる
そんな「旅の視点」がガラッと変わるはずです。
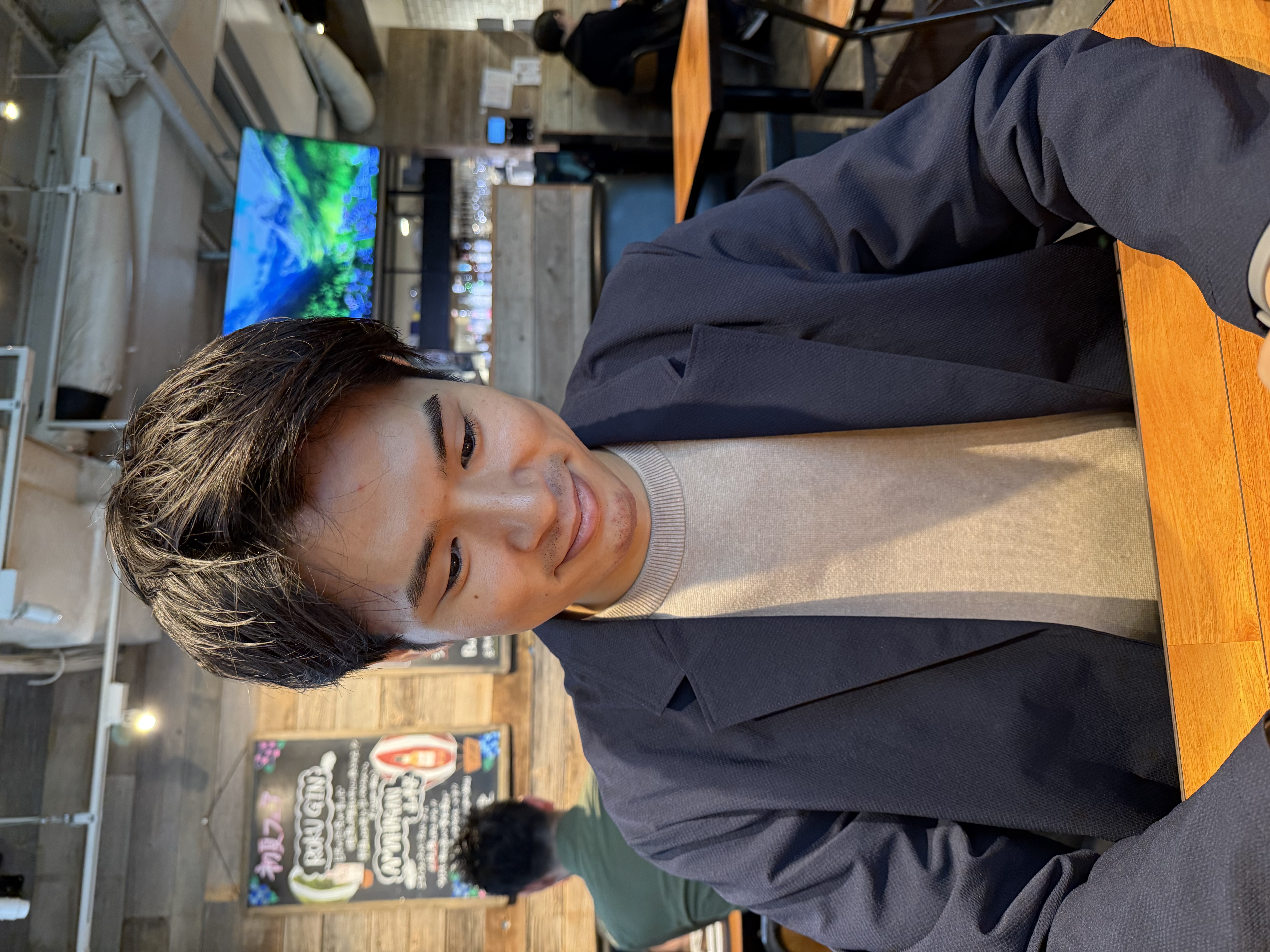
りょう
いろいろなことを考えるエンジニア